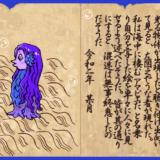Be My Valentine

もくじ
男性がプレゼントを贈ることが多い

日本の『バレンタインデー/Valentine’s Day』は、実質「女性が男性にチョコレートを贈る日」になっていると思います。
しかしアメリカでは、性別に限らず「チョコレート、花、カード」等を人に贈るのが定番となっています。どちらかといえば、男性が誰かにプレゼントを用意するイメージが強いとアメリカ人は述べています。
とくに思春期以降になると、意中の相手に上記のようなプレゼントを渡す男性が増えてきます。中には交際者/配偶者にジュエリーを贈る人もいます。
私はバレンタインに、妻に宝石をプレゼントした。
…かといって、恋愛一辺倒のイベントではなく、学校のクラスメートや家族とも「バレンタインデー」が祝われることもあります。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
※「ホワイトデー」は日本発祥の行事とされています。

バレンタインデーに、日本の女性が同僚やクラスメートにチョコレートを配る風習は、『義理チョコ』文化と呼ばれている。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
アメリカの「バレンタインデー」にまつわる重要な熟語を2つご紹介します。いずれも「愛」に関わる重大な英語となっています。
Significant other(最も大切な人)

『Significant other/スィグニフィカント・アザー』という言葉があります。 自分の人生で最も大切な人という意味です。『Other』は自分以外の他者を意味します。よって、基本的に家族や親友ではなく、恋人か配偶者に対して使う言葉となっています。
アメリカの「バレンタインデー」は、この『Significant other』をより大切に思う日となっています。
バレンタインデーになると、日本人女性はチョコレートを複数の男性に渡すが、アメリカでは、男性が、自分の大切な1人の人に花やチョコレートを贈ることが多い。
Be my Valentine(私のバレンタインになって)
『Be my Valentine』というフレーズもよく知られています。直訳すると「私のバレンタインになってください。」となります。
「バレンタインデー」当日のデートに誘う際のセリフとして使用されます。
私のバレンタインになってくれますか?(私とバレンタインを過ごしてくれますか?)
ちなみに、『Be my Valentine』に同意するなら『Yes』と答えれば良いそうですが、具体的なことはセリフに含まれていません。
よって、アメリカ人ですら「何と返答すれば良いの?」「バレンタインになるってどういう意味?」という相談をネットに投稿する人もけっこう見られます。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
子供は「バレンタインカード」を学校に持参する

「バレンタインの授業」がある
私が日本で通った小学校では、バレンタインチョコの持ち込みは禁止でした。他校でも、禁止までいかなくても、大っぴらに学校側が「バレンタインデー」を盛り上げるようなことは無いと思います。
ところが、アメリカの小学校では2月14日の「バレンタインデー」を重要視していました。授業時間内に「バレンタインカードの交換会」も行われます。
私が子供の頃、教室でバレンタインカードを配るための時間が設けられていました。
※『Hand out』 (配布する)
私の通っていたアメリカの小学校では、順番に子供が教室を巡回しながら、自分のカードを一人一人に手渡しで配る時間が設けられていました。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
クラス全員分のカードを持ってくる人もいるし、仲の良い友達にのみ配る人もいました。中には何も持ってこない子供や、1枚も貰えていない子供もいました。
子供が箱を持参し、その中にカードやチョコを投函してもらう方式もあるそうです。好きな相手が入れたカードには、何が書いてあるのかを、あとから確かめるドキドキ感が味わえます。
≪関連記事≫アメリカで、バレンタインよりもチョコレートが売れる行事といえば? イースター・Easterとは?アメリカのイースターエッグ祭
イースター・Easterとは?アメリカのイースターエッグ祭
アメリカは、カード文化の国
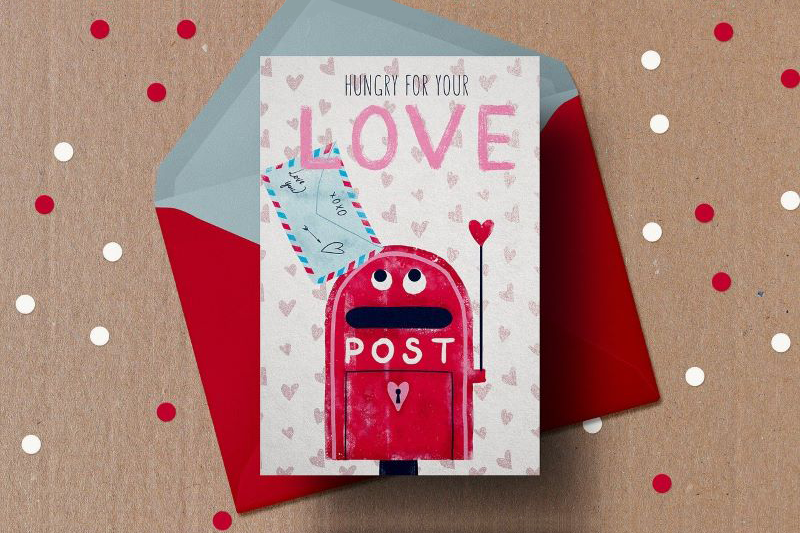
『Greeting card/グリーティングカード』という、主にカラフルなイラストなどがデザインされたメッセージカードがあります。このようなカードを、アメリカでは年間を通して贈り合う文化があります。
アメリカの「バレンタインデー」は、小学校に限らず、国全体でも多くのカードが贈られる日となっています。
≪海外サイト≫GREETING CARD ASSOTIATION 「グリーティングカードの歴史」
市販されているカードには、『Happy Valentine’s Day』や『Be my Valentine/私の恋人になって』などの言葉がプリントしてあります。日本の年賀状における「謹賀新年」や「あけましておめでとう」のような、テンプレに沿った「バレンタイン用の言葉」がカードに印刷されています。
Good Housekeeping によると、アメリカでは毎年2月14日に「1億4500万枚」のバレンタインカードが交換に使用されるそうです。
しかも、これは大人をターゲットにした統計結果であり、子供たちが教室で交換し合うカードの枚数のすべては含まれません。
つまり、実際の枚数は更に多く、正確に把握できていないということです。
いかにバレンタインがアメリカで重要な日なのかが理解できる数字ですね。1913年にグリーティングカードメーカーのホールマーク(Hallmark Cards,Inc.)が最初にバレンタインカードを市販してから、伝統的にアメリカ人に親しまれ続けている文化といえます。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
そして微笑ましい事実として、もっともバレンタインカードを受け取る職業は学校の教師です。
ちなみに小学校の低学年であれば「バレンタイン=恋愛」という意識はまだ弱いですが、思春期以降になると、バレンタインデーを、恋愛関係を深めるきっかけにするかたちに移行していくようです。
≪関連記事≫アメリカにはない日本独自のお返し文化といえば? 『WhiteDay/ホワイトデー』英語での発音のコツは?
『WhiteDay/ホワイトデー』英語での発音のコツは?
バレンタインデーの由来が怖い?

バレンタインは、聖人の名前
バレンタインという言葉は、「聖ヴァレンティヌス」というローマ帝国時代の聖職者の名前から来ています。
同名の有名ブランドのように「ヴァレンティノ」とも呼ばれるお名前で、英語表記だとお馴染みの『Valentine』になるので、日本では「聖バレンタイン」と表記されます。
『Valentine’s Day』の英語での発音は…
※青文字にアクセント
これを翻訳すると、「バレンタイン(ズ) デー」すなわち、「バレンタインという人物のための日」という意味になるのです。
聖バレンタインの殉教日が2月14日

なぜ、「バレンタインデーの由来が怖い」という声があがるのかというと、この聖バレンタインがローマで処刑された日が2月14日とされているからです。
あくまで伝説上の人物の逸話なので、諸説ありますが、当時のローマ帝国では、若い兵士の結婚が違法だったそうです。理由は、結婚してしまうと彼らが戦争に行きたがらなくなるから。
それを不憫に思った聖バレンタインは、ローマ帝国側に知られぬよう、密かに若者たちを結婚させていたところ、それが発覚してしまい、投獄されて処刑となったそうです。

別の伝説では、同じく投獄された聖バレンタインが、看守の娘と恋に落ちたエピソードもあります。
そして、彼が2月14日に処刑される直前に『From your Valentine』と署名された手紙を娘に渡したことから「バレンタインカード」という後世の習慣につながったともいわれています。
興味深いことに、上記2つのエピソードは「それぞれ別々のバレンタイン」という人物に関する言い伝えである点です。
≪海外サイト≫ Country Living きっとあなたも驚く「バレンタインデー」真実の歴史
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
その後、「恋人たちの守護神」として、聖バレンタインは聖人として祭られるようになり、形を変えて現在の「バレンタインデー」へと至ります。
アメリカ人であっても、誰もがバレンタインデーの起源を知っているわけではない。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
スマ留「最大半額の留学エージェント」のご案内

10か国以上から選べる格安留学
忙しい社会人の方でも「最短1週間」からの留学が可能なスマ留のご紹介です。なかなか時間が確保できない方の語学留学を実現し、気軽に留学できるプランも用意されているので、ぜひおすすめしたいサービスです。
スマ留の良いところは「自分の語学力に合ったクラス」で授業が受けられる点です。今現在「語学力に不安がある方」も、チェックしてみてください。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授

「留学生に優しい国」といわれるオーストラリアや、「日本からいちばん近い英語公用語の国」であるフィリピン、そしてアメリカ・イギリス・アイルランド・カナダなど、「英語を母国語」とする国々も見られます。
また、今や「世界有数の大都市」となったドバイや、「地中海に浮かぶ小さな島国」マルタへの留学も選べるなどバラエティに富んでいます。

 ふわふわ教授
ふわふわ教授
スマ留が選ばれるポイント

 ふわふわ教授
ふわふわ教授
①留学費用が従来の最大半額
スマ留では徹底して余計なマージンをカットすることにより、驚きの低価格で留学ができるようになりました。また、語学学校の「空き時間」や「空き場所」を有効活用したシステムのため、安いのに他社と同じクオリティの授業が受けられる点も嬉しいポイントです。
正に「日本中の人々に異文化交流を経験してほしい」というコンセプト通りの良心的な価格設定になっています。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
「安さの理由」について詳しくはコチラ⇒ スマ留の安さの秘密
②シンプルな料金体系
スマ留の留学費用は「パッケージ料金」です。よって、最初に提示された金額から上がらず「追加費用なしでの留学」が可能です。行きたい国と期間さえ決まれば、留学費用が明確に分かる料金表がWEB上にも用意されています。
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
選べる2つの料金プラン⇒ 留学の費用・プラン
③同一価格で語学学校が自由に選べる

スマ留の料金は、「留学先とプラン」が決まれば同一価格です。よって、費用を気にせず語学学校を自由に選ぶことができます。一般的な留学サービスでは、スクールによって値段が変わるので、ここも嬉しいポイントです。
ただし、人気の学校はすぐに空きがなくなりますので、学校選定の段階になったら早めにご決定してくださいね。
④充実の英語学習サポート
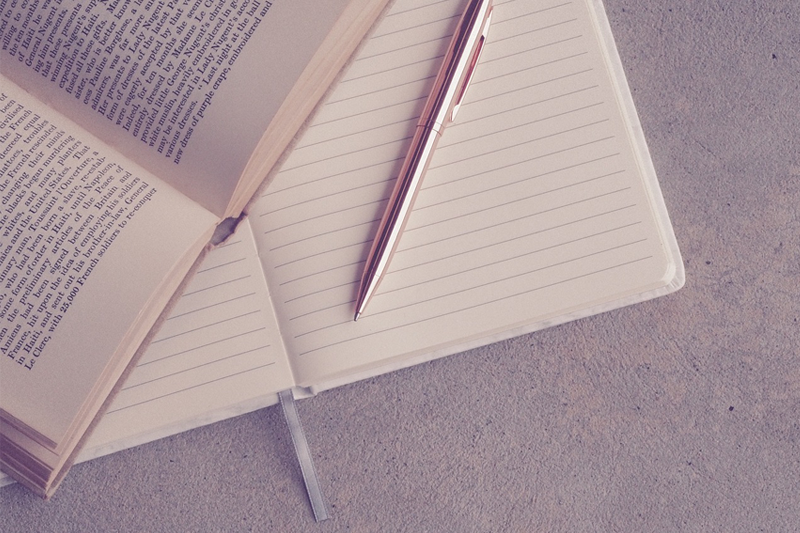
スマ留では、現地での学習とは別に2つのサービスによって英語学習サポートを強化しています。
オンライン英会話の「ネイティブキャンプ」とオールインワン英語学習アプリの「レシピー(旧ポリグロッツ)」が6カ月間活用でき、さらに英語力向上を目指せます。
※「スマ留スタンダードプラン」のみでの適用です。1つ下のグレード「スマ留ライトプラン」には含まれない点をご了承くださいませ。
⑤お申し込みから留学までの準備が、全てLINE上で完結

スマ留では最初の「無料カウンセリング」からお申込みまでLINEのやり取りのみで完結できます。渡航前のお客様の留学時期に合わせて、「スマ留公式LINE」から必要な準備のご案内が送られてきます。
さらに、留学中の緊急時にも「LINEでのお問合せ」に対応しているので安心ですね。
以上、駆け足でのご紹介でしたが、スマ留の魅力が少しでも伝わりましたら幸いです。もちろん、「スマ留の公式サイト」には、より詳しい情報が盛りだくさんで掲載されていますのでご興味ある方はぜひチェックしてみてくださいね。
スマ留公式サイト⇒ 留学ならスマ留(スマートな留学)
 ふわふわ教授
ふわふわ教授
本日も最後までお読みいただき誠にありがとうございます。